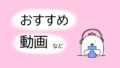あるきっかけから心穏やかに明るく生きる方法を探求している「にわとり印のごきげんブログ」。
作成者のNikoです。
思春期にさしかかる10歳前後のお子さんがいる方、
特に私のように、思春期の子育てに自信のない方に、ぜひ読んでいただきたい!
今日ご紹介するのは、高濱正伸さんの「子育ては、10歳が分かれ目。」です。

「子育ては、10歳が分かれ目。」ってどんな本?
思春期における親のあり方、心構えをわかりやすく教えてくれる本
「子育ては、10歳が分かれ目。」は、思春期における親のあり方、心構えなどが多くのエピソードとともに大変わかりやすく書かれている本です。
特に、思春期における親の役割、特に同性の親の役割の重要性と、その役割をまっとうするための具体的な方法について書かれています。
同性の親が、生きていく上での知恵と知識を伝授していくことが、十歳からの子育ての重要な鍵になるーーこれが、本書の柱です。
高濱正伸著「子育ては、10歳が分かれ目。」PHP文庫 P11 プロローグより引用

やむを得ない事情で両親揃っての子育てが難しいご家庭もあるかもしれませんが、
身近な誰かにその役割を担ってもらう(高濱さんの場合は伯父さんだったそう)という意味でも、役割を知っておくことがとても役に立つと思います。
著者は高濱正伸さん
「子育ては、10歳が分かれ目。」の著者は、全国規模で展開され大人気の学習塾「花まる学習会」代表の高濱正伸さんです。
「メシが食える大人」そして「魅力的な人」を育てるために意欲と思考力を伸ばす学習法を提案、実践されています。
公立学校向けの授業や研修支援を行っているほか、「メシが食える大人になる!よのなかルールブック」「伸び続ける子が育つ お母さんの習慣」など、著書も多数出版されています。
この本の構成
この本はプロローグとあとがきのほか、第1~5章で構成されています。
全261ページです。
イメージをつかみやすいよう各章のタイトルを下記に引用させていただきます。
第1章 「男女の違い」を知れば家庭は変わる
第2章 十歳の「子離れ宣言」からの育て方
第3章 お母さんの役割
第4章 お父さんの役割
第5章 思春期は親の真価が問われるとき
高濱正伸著「子育ては、10歳が分かれ目。」PHP文庫 P16 目次より引用
「子育ては、10歳が分かれ目。」のポイント

私にとって「ここは特に読んでよかった!」というポイントをまとめています
夫婦がお互いの違いを理解することの大切さ
高濱さんは、育児に積極的にかかわろうとするお父さんが増えている一方で、子を持つ前から夫婦が共にお互いの嫌なところに目がいってしまっていて、実際は足並みが揃っていないケースが多いように感じているそうです。

・・・ドキッ
その原因は「夫婦が互いの違いを知らないこと」にあると高濱さんは考えます。
「平等」であっても「同質」ではないのが男と女。人間関係が希薄になってしまったこともあって、誰にもお互いの違いを教わらないまま大人になった男女が続々と社会人になっている現状がある、と高濱さんは指摘しています。
(前略)結婚の形も多様になりつつあります。しかし、そこでも問題の本質は同じです。要は他者と暮らしていくためには、自分と異なる相手の心のありようを、お互い想像力と傾聴力をもって知ろうとすることが大事なのです。
高濱正伸著「子育ては、10歳が分かれ目。」PHP文庫 P29より引用

※夫婦がお互いを理解するためのヒントとしてこちらの本もおすすめです
子どもが10歳になったら行いたい「子離れ宣言」
私はいつも、講演や著書の中で、「子育てには二つの時期があります」と説明しています。
一つは四歳から九歳ぐらいまでの「赤い箱」の時代。いわばオタマジャクシの時代です。
二つめは、十一歳から十八歳までの「青い箱」の時代。カエルの時代です。
九歳から十一歳まではその変わり目で、手足が生えてきたオタマジャクシのように、どっちつかずの不安定な時期です。
高濱正伸著「子育ては、10歳が分かれ目。」PHP文庫 P45より引用
高濱さんは「オタマジャクシ」から「カエル」ぐらい心も体も大きく変化する10歳の頃に
「子離れ宣言」をして、それまでの子供扱いをやめ、親が子どもと本音の付き合いをしていくことが大切であると考えています。
(高濱さんがおすすめしているのは、小学5年生に上がった4月)

子どもの自立心が育ってくるこの時期に合わせて、親も意識を変えなければいけない、ということですね。
特に母親にとって、子離れは最大の難所
特に、子供をおなかに宿してから世話をし続けてきた母親にとって、思春期の子離れは難所であると高濱さんはいいます。
それでもやはり、思春期を機に、お母さんは上手に子離れしていかなければなりません。ここで子離れできるかどうかは、子どもの将来のみならず、親子関係の将来をも左右します。逆説的に聞こえそうですが、ここでしっかり親離れ、子離れができた親子のほうが、自立した大人同士、将来にわたっていい関係でいられるのです。
高濱正伸著「子育ては、10歳が分かれ目。」PHP文庫 P176より引用
子どもが成長するにつれて壁にぶちあたったり、辛いことを経験するのは普通のこと。そうした沢山の経験を積むことが子どもを大人にさせてくれる。
子どもからそうした経験を取り上げてしまわないように、10歳になるのを境に様々な手出し口出しをやめなければいけない。

やっぱり何かと手出し口出ししたくなってしまう私。耳が痛いです・・・
子どもを心配で仕方なくても辛くても、乗り越えるしかない難所だと高濱さんはいいます。
この難所を乗り越えるために必要なものは、「信じること」です。
高濱正伸著「子育ては、10歳が分かれ目。」PHP文庫 P179より引用
子ども自身の力を信じ、これまで自分が注いできた愛情を信じ、今度は自分自身の人生を充実させていくことが重要なのだそうです。
思春期には子供にどんどん「毒」を出してもらうべき
思春期というのは、本来、誰もが心に「毒」を持つ時期です。子どもから大人に変わる関門で、多感な心が色々な真実を知ってしまうからです。
高濱正伸著「子育ては、10歳が分かれ目。」PHP文庫 P8より引用
親や先生から教わってきた理想の世界と現実の社会のギャップに気づき、苦しみながら生きているのが思春期の子ども達。
親を軽視したり反抗したりと「毒」を出しながら、秘密を持つなどして友達との関係の方を大切にしていくのがこの年頃の子ども達なのだそうです。
この時期に、従順で反発や葛藤がない子はむしろ物事を深く考えていない危険な状態である、と高濱さんは指摘しています。

親は子供が生意気を言ったり秘密を持ったりすることを成長の証として、余裕をもって受け止めてあげられると良いのですね。・・・頑張ろう。
読んでみての感想
高濱さんがこれまで数多くのご夫婦や子供たちを見てこられた経験が沢山語られていて、さらにユーモアのある文章でとても読みやすい本でした。
上記したポイント以外にも、重要だと感じたところが沢山ありました。
- 親自身が本音を語ること(清く正しいことや、偏りのない考えではない)
- 異性の親は、思春期を境にフェードアウトしていき、パートナーを支える立場になること
- 子供の自立を楽しみにすること
- パートナーは犬(愛すべき、自分とは全く異なる生き物という意)だと考え、関係がうまく行くように努力すること
↑こういう本も書かれているのですね(^^

このブログのホームにも記載したのですが、
私自身は思春期に家庭が非常にゴタゴタしていたため、「自分まで荒れたらこの家はおしまいだ・・・」と思い、環境に過剰適応する良い子になってしまって、反抗期というものを通過しないまま大人になってしまいました。

まさに、高濱さんがこの本で危険視している「葛藤を持たない子供」でした・・・!
この本で「思春期に毒を出しておかないと、後にゆがんだ形であらわれる」旨が指摘されているように、私の場合は結婚して子育てが始まってからその弊害が出てきてしまったので、わが子には同じことを繰り返したくない、という思いがあります。
しかし反抗期を経験していない身としては、わが子に訪れる反抗期が正直とても不安でした。
この本はそんなとき(現在10歳を過ぎた我が家の長女がまだ7歳ぐらいの頃)、たまたま書店のレジ横に積まれてあるのが目に留まった本です。
タイトルのインパクトが強く、直感的に「何か助けになってくれそうだ・・・」という気持ちで読みました。この記事を書くにあたりもう一度読んでみて、あのときの直感は当たったなぁ、この本を買ってよかったなぁ・・・と感じます。この本のようにできていないことも多いなと、改めてハッとさせられました。
自分の価値観だけでは絶対にわからなかったことを、沢山教えてくれる本でした。
特に、思春期は「秘密」「毒」「反抗」があっていいということ。

「この時期の毒はむしろ大歓迎」と、改めて覚悟しておかないと・・・!
ただ、長女がまだ幼児のとき(頭の中の大爆発を起こす前)、私の余裕がなく思いっきり甘えさせてあげられなかったという心残りがあって、今でもごくたまに「抱っこ」など甘えてくる時があるので、その時だけはチャンスとばかりに抱っこしてあげようと思います。
あとは基本的に大人と大人として対応しよう。
秘密を持ったり反抗したりした時も慌てないで、そういうものだと落ち着こう。
今後も手出し口出ししたくなる時が沢山あると思うので、そんな時に繰り返しこの本を読みたいと思うし、時間が無いときは自分でこの記事を読み返したいと思っています(笑)
最後に、この本の最終章の文がとても心に残ったので引用させていただきます。
最後にお母さん、お父さんにもう一度お願いしたいのは、子育てのゴールをくれぐれも見誤らないでほしいということです。それは子どもをいい大学、いい会社に入れることではないはずです。
どうか忘れないでください。子育ての一番の目標は、子供が「人間力」あふれる大人に育つこと。「メシが食える」「モテて魅力のある」大人に育つことです。
(中略)子どもが立派に独立したら、また夫婦だけの暮らしを楽しむ。そんな豊かな将来が、みなさんを待っていますように。
高濱正伸著「子育ては、10歳が分かれ目。」PHP文庫 P256より引用