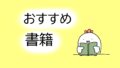あるきっかけから心穏やかに明るく生きる方法を探求している「にわとり印のごきげんブログ」。
作成者のNikoです。
春からドラマ化されるという紹介を見て、あらすじを見たらすごく気になり。
早速購入して読んでみました。朱野帰子さんの小説、「対岸の家事」です。

小説「対岸の家事」ってどんな本?
ある専業主婦の女性が近隣の人達との繋がりを通して、自分の生き方を考えていくお話
「対岸の家事」は、2018年に単行本が、2021年に文庫版が講談社より刊行された小説です。
この物語は、主人公である専業主婦の村上詩穂と、その家族である夫・虎朗&娘の苺ちゃん、そして詩穂の住む地域のご近所との人々との関わり合いについて書かれた長編小説です。
主人公の詩穂は、働く女性が多い世の中での専業主婦という立場について悩みながらも、人とのかかわりを通して自分の生き方について考え、成長していきます。
この小説で示す「家事」には「育児」も含まれているようです。

現代を生きる子育て世代の日常のについて書かれた物語で、描写が本当にリアル。
現在子育てをしている方には特に共感できる部分が多いのではないかと思います。
講談社文庫のあらすじ紹介
家族のために「家事をすること」を仕事に選んだ詩穂。娘と二人だけの、繰り返される毎日。幸せなはずなのに自分の選択が正しかったのか迷う彼女の街には、性別や立場が違っても様々な現実に苦しむ人たちがいた。誰にも頼れず、限界を迎える彼らに、詩穂は優しく寄り添い、自分にできることを考え始めるーー
朱野帰子「対岸の家事」講談社文庫 背表紙より引用
簡単なあらすじ&みどころ
以下、簡単なあらすじを記載しています。

簡素なものですが、「何も知らないまっさらな状態で小説(ドラマ)を見たい!」という方はご注意くださいね。
↓↓↓
14歳で母親を亡くして以来、実家で家事のすべてを引き受けてきた詩穂は、18歳のときに父を残して実家を出ました。
その後、飲食店勤務のサラリーマン・虎朗と結婚。専業主婦として2歳の娘・苺を育てています。
詩穂は子育てをしていく中で、近隣の住人である
マンション隣人で2児のワーキングマザーである礼子、
1歳の娘のために育児休暇中であるエリート公務員の中谷、
70歳の先輩専業主婦の坂上さんとその娘、
地域の小児科医に嫁いだ晶子らと知り合っていきます。
最初は相容れない部分も多かったものの、交流を深めていくうちに徐々にお互いの立場を理解し、助け合うようになっていく一同。
そんな中、詩穂を標的としたある事件が起きます。
事件がどのような方向に向かっていくのか、
近隣の人達との交流を通して、詩穂はどのように自らの生き方を見つめ、成長していくのか・・・
というところが見どころの物語です。
この本の構成
この小説は最初に目次と主な登場人物の紹介があり、
プロローグ&第一話~第七話&エピローグで構成されています。

文庫版では、夫・虎朗目線のアナザーストーリーである「文庫版限定付録 うちの奥さん、主婦だけど。」が掲載されています。ほのぼのしたお話でした。
全430ページの長編小説です。
「対岸の家事」の作者は朱野帰子さん
作者である朱野帰子さんは、2009年に「マタタビ潔子の猫魂」で第四回ダ・ヴィンチ文学賞を受賞された作家です。
「対岸の家事」同様、ドラマ化された小説として「わたし、定時で帰ります。ーライジングー」があります。
この小説の文庫版のあとがきで、この物語を書いたきっかけについて朱野さんはこのようにつづっています。
(前略)だけど、じゃあ、誰が家事をやるんだろう?
大学の後輩が「仕事じゃない」と言われたこの労働は今もなくなってはいません。
(中略)専業主婦が絶滅しかかっている世界を書いてみたくなりました。
朱野帰子「対岸の家事」講談社文庫 P430「文庫版に寄せて」より引用
家事をテーマに書くことは難しく、この小説は朱野さんが書くことを決めてから書き終わるまでに5年位の時間を要したそうです。
読んでみての感想
描写がリアルで、自分の生き方や子育てについて自然に考えさせられ、たびたび涙を流しながら物語にぐいぐい引き込まれていきました。
前半は特に、刺激的というよりは静かな物語なんですが、後半はどうなっちゃうんだろうとちょっとハラハラする展開もあり。
結末に近づくとしっかりと伏線の回収もあり。

読者の心に染みる言葉もとにかく沢山あって、とても読み応えのある小説でした!
詩穂や中谷の過去と苦悩、坂上さんと詩穂が初めて出会った時の話や、生前の詩穂と母との会話など・・・(うーん書ききれない)じーんとくるポイントが沢山ありました。
特に私が好きなのは、詩穂と2歳の娘・苺の日常を切り取ったこの部分。
「ママ、見て!」
「なあに」
隣に寝転がると、天井に光の玉が幾つも連なって揺れていた。太陽の光がベランダのメダカ鉢に反射して映っているのだ。しばらく二人で光の揺れを眺めた。
(中略)これは正しい暮らしではないのかもしれない。自分は時代の趨勢のことを何も知らないのかもしれない。でも、そんなことは全部忘れて、「きれいね」とか「ぶどうみたいに見えるね」とか、言い合うこの時間は、きっと将来、詩穂の宝物になるだろう。
思い出すだけで、泣きたくなるような、まばゆい記憶になるだろう。
朱野帰子「対岸の家事」講談社文庫 P87より引用

ドラマ化は楽しみだけど、小説もとてもおすすめです!
主人公の詩穂については、「静かだけれど覚悟がある強い女性だ、いいお母さんだな」と感じました。
畳を丁寧に拭いたり、節約をしたり、娘・苺ちゃんへの優しい対応をしていたりと「専業主婦のプロや・・・!」と背筋が伸びる部分も多々ありましたが、励まされる言葉も沢山ありました。
ちなみに育った家庭が複雑であるところや、子供の年齢が近いところ、「同時に2つのことができない」と自分の要領の悪さを自覚しているところなどが私と似ていて、何かと感情移入してしまいました。
現在、家事育児とウェブライティングの仕事をしている私ですが、過去にはワーキングママとして外で働いていた時代も、完全に専業主婦だった時代もあります。
2児を育てるワーキングママ・礼子の日常を読んで、子どものことを満足にできない苛立ちや罪悪感、子どもが体調を崩した時の絶望感のようなものも思い出しましたし、
詩穂のように完全に専業主婦だった時に感じた、昼間が途方もなく長く感じられる空虚感も、「今の時代に専業主婦でいる後ろめたさ」のようなものも思い出しながら読みました。
(このブログを書くきっかけとなった頭の中の大爆発を起こしたのも、専業主婦の時代でした。)
ワーキングママも、専業主婦も、どちらも別の部分で大変だなと思うし、この物語を読んで改めてそれを感じます。
女性が働く時代、という「大きな風」は吹いたけれど、この小説の中で詩穂が気づくように「正しい暮らし」などというものは本当は無いのだと思います。
皆それぞれが自分の向き不向きや環境と相談しながら、大事な役割を担って精一杯頑張っているんだよな・・・
この小説のように(この小説の登場人物達も最初は互いに相容れなかったのだけれど)、
お互いに対岸にいる人を批判するのではなくて、協力していく関係になれたら。そういう世界であったら・・・と。
「いいものを見せてもらったな」という気持ちでいっぱいです。

その他の記事もぜひ➩にわとり印のごきげんブログホーム